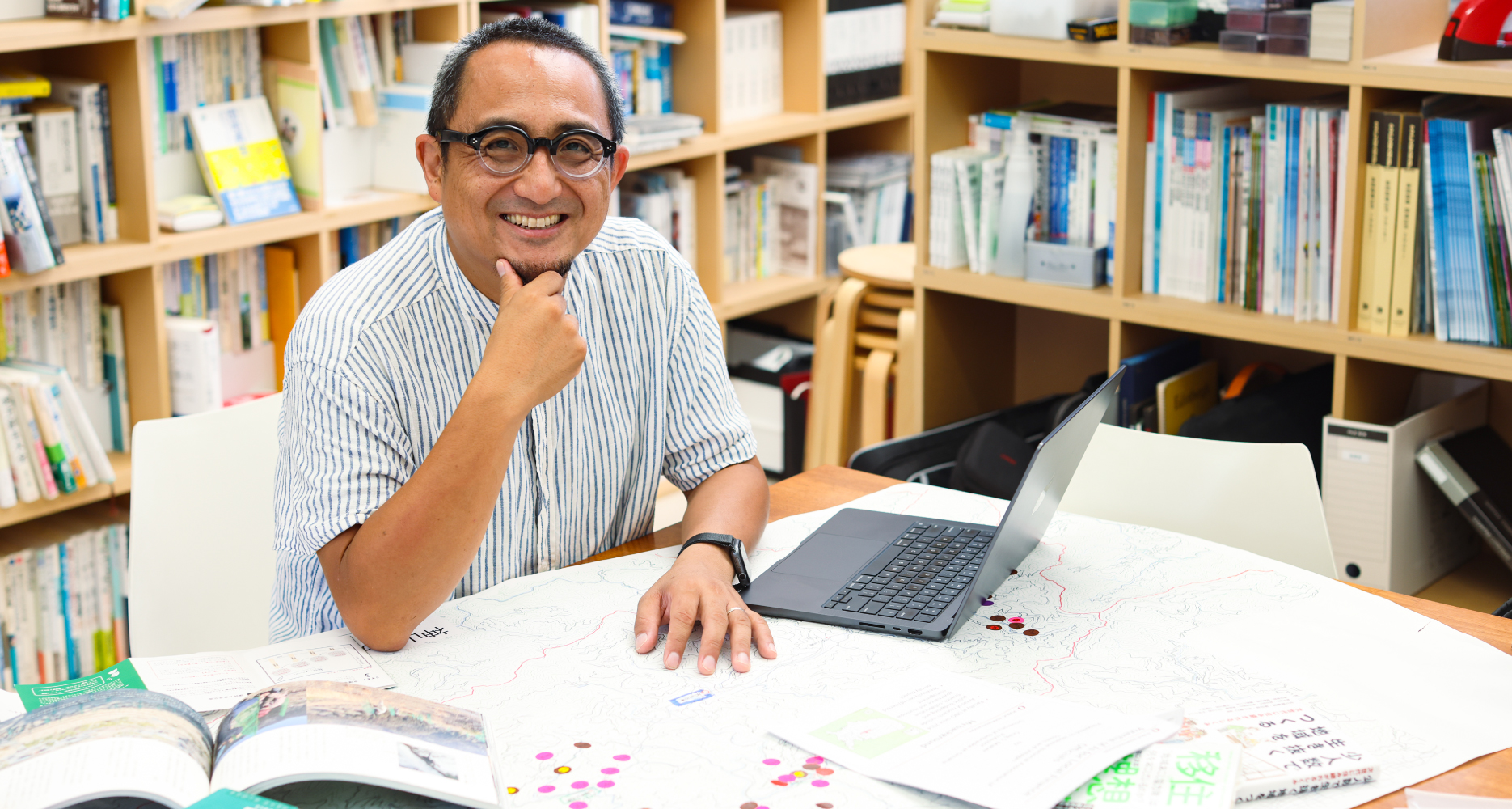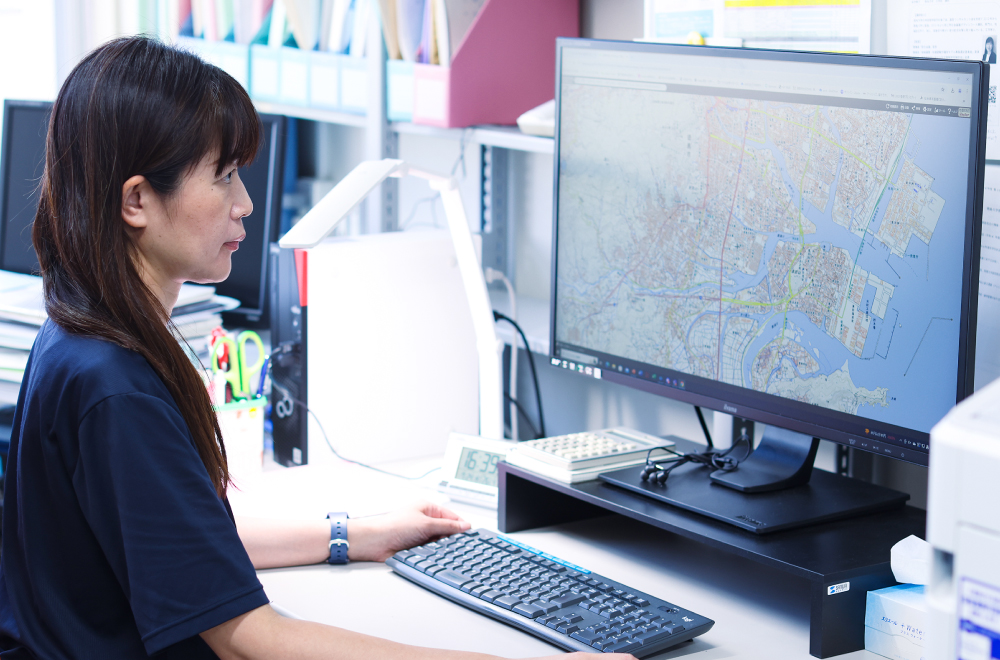7つの学位プログラム社会基盤システムプログラムCivil and Environmental System Program
防災科学分野、地域環境分野、構造・材料分野、地域創成分野、臨床心理学分野の構成の下に、現代社会の基幹を成す科学技術分野である社会基盤学、社会科学、あるいは人間科学の深化と、文理横断的な視野を含めた広い視野に立って他分野との融合化をさらに発展させることができる研究者や技術者を養成することを通して、次世代の持続可能社会に貢献することを目的とする。
文理横断的な専門知識・技能をふまえ、地域再生、防災・減災、インフラ整備、環境問題等の社会の諸課題の解決に取り組むとともに、持続可能な地域づくりや地域・環境計画など を通して、安全で快適な社会生活基盤ならびに社会文化環境を創造できる高度専門職業人・研究者を養成する。

超高齢社会型災害に適応した避難方法
~「防災×福祉」で逃げ遅れ0を目指す~
日本の高齢化と災害リスクの深刻化
日本は高齢化率が28%を超える超高齢社会であると同時に災害大国です。東日本大震災では死者の約3分の2が60歳以上でした。平成30年7月豪雨により町全域が浸水した岡山県倉敷市真備町では、死者の約80%が70代以上の後期高齢者でした。令和2年7月豪雨では球磨川が氾濫し、高齢者施設の入居者14名が逃げ遅れて死亡しました。超高齢社会型災害を前提としたハード・ソフト対策が行われなければ、自然災害で亡くなる高齢者は増え続けるでしょう。
高齢者の避難支援における福祉の役割
東日本大震災において、逃げるように伝えたのは、「家族・同居者」が約3割、「近所の人・友人」も同じく約3割、約2割が福祉関係者でした。いかに普段から近所や福祉とのつながりを持つかが課題です。世界一の高齢化率である日本において、逃げ遅れ防止対策のカギとなるのは福祉です。私は、防災と福祉に関係する人・もの・情報といった資源を有機的につなぎながら、超高齢社会型災害に適応した避難方法について研究しています。
被災事例調査に基づく避難行動分析
高齢者は逃げ遅れる傾向にあります。避難行動を阻害する要因を明らかにするためには、数多くの被災事例を研究する必要があります。方法として、被災地の現地調査や被災者へのインタビュー調査を行います。災害の痕跡は復旧作業と共に失われていきますので、安全に留意しながらできるだけ早く現地を調査します。災害の発生原因を把握した上で、避難行動を検証します。これまでに調査した高齢者施設等の被災事例は100件を超え、国内有数のデータベースになりつつあります。蓄積された知見をもとに、避難計画やBCPの改善策を関係機関へ提案します。
グローバルな視点からの高齢化社会型災害対策
日本は世界の最先端を走る「高齢化」の先進国です。将来的には開発途上地域と呼ばれるアジアの国々も軒並み高齢化社会に突入します。超高齢社会型災害に適応した避難方法は、そのような国々でも役立ちます。ネガティブな響きのある「高齢化」というワードですが、それをグローバルな視点でとらえ直すことで、そこに新しい価値観を見いだすことが可能になります。
超高齢社会における災害に備える
2050年の日本の高齢化率は37.1%に達する見込みです。近い将来発生すると予想されている首都直下地震や南海トラフ地震は、確実に超高齢社会型災害となります。超高齢社会型災害に適応した避難方法の実効性を高め、研究成果を社会へ還元します。

金井 純子准教授
博士課程は理論を実践できる貴重な場です。皆さんが修士課程で構築した理論や技術が、防災システム全体のどこに位置し何と関係するか、社会課題をどのように解決することができるのかを考えて下さい。安全・安心で持続可能な社会をつくるために、多くの若い学生が防災分野の研究にチャレンジしてくれることを期待したいです。
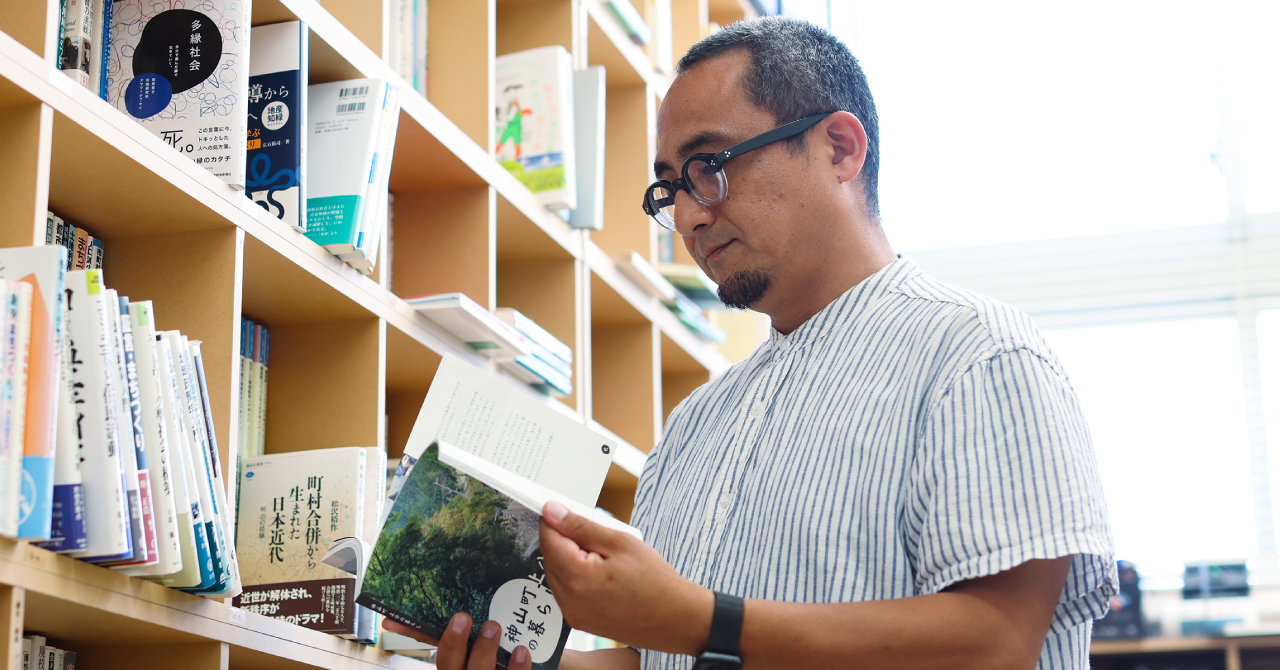
市民を核とした
自律的なまちづくりに向けたプロセスデザイン
人口減少時代に地域の可能性を最大化する
人口減少・少子高齢化が進み、地域の衰退や存続が危ぶまれている現状があります。一方で、情報インフラの発達や人々の移動の活発化は、「人口」では測れない地域の可能性を育んできました。こうした可能性を最大限に活かすのか、無駄にしてしまうのかは地域側の戦略にかかっているとも言えます。地域に関わるそれぞれの立場で、どのような戦略を立て、状況変化に上手に対応していく方法を提供することが研究サイドから地域に貢献できる重要なポイントです。
地域の主体的な変革を促すための戦略とは?
どのような素晴らしい計画を外から提示しても、地域側がそれを認識し、実行に移さなければ地域の状況変化は生まれません。いかにしてリアリシティのある対策を立案し、実行に移せるか。状況認識から自律化に至るまでのプロセス、市民が主体的にデザインできるための支援策を検討することを目的としています。
ワークショップで探る!地域を変えるための第一歩
地域に関わる人々の認識がどうなっているのか、どの様にその認識が変化していくのか。ワークショップ等、地域支援の方策や有効な施策を実証的に開発し、社会に還元してく、という方法をとっています。
地域活性化の推進力に!実践で育む人材と地域
研究を通じて様々なワークショップや人材育成プログラムを開発してきましたし、考え方の社会還元も進めてきました。例えば、地域おこし協力隊をに向けた人材育成キットは、協力隊や若手行政職員のみならず、社会福祉協議会のスタッフやJICA海外協力隊向けの研修ツールとしても活用されています。また、住民向けのワークショップも福島県から沖縄県に至る各地で実施され、様々な活動が生まれてきています。
さらなる展開に向けて地域の未来を共創する
人口減少下でも、様々な外部者の力も借りながら、上手に地域が運営されていくことができれば、現在各地で叫ばれている「地域の危機」もきっと乗り越えられることでしょう。

田口 太郎教授
地域計画の分野では、研究が社会とダイレクトに繋がっています。文字通り、良い研究成果が直接的に地域社会に良い風を吹かすと言ってもよいでしょう。そのためには、一人ひとりが自らの経験をベースとした問題意識を持ち、問題意識をベースとして、より良い提案を論理的に組み立てていく、ということが大切です。そして研究を通じて、地域が大きく変化していく様を見ることが出来ます。是非、一緒により良い地域の未来を考えましょう。

長田 有加里さん
- 社会基盤システムプログラム
- 社会人博士
多文化共生まちづくりの実務で直面する課題を体系的に捉え、政策レベルでコミットする高い能力を身に付ける必要性を感じたからです。私は地域の人びとと外国籍をもつ人びとの双方が活躍する多文化共生まちづくりの実務を担っています。そこでは草の根の現場と政策デザイン双方からのアプローチが求められています。